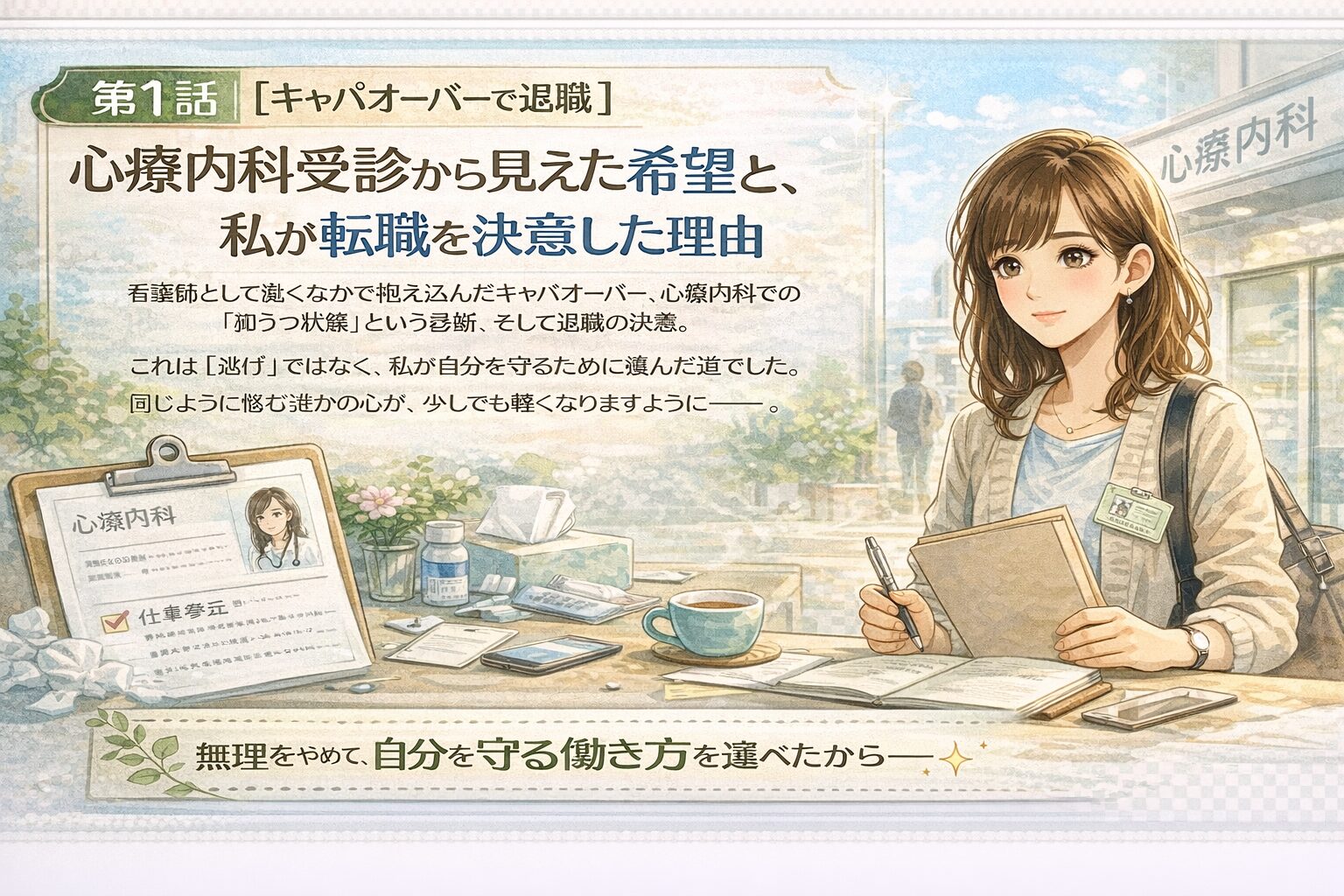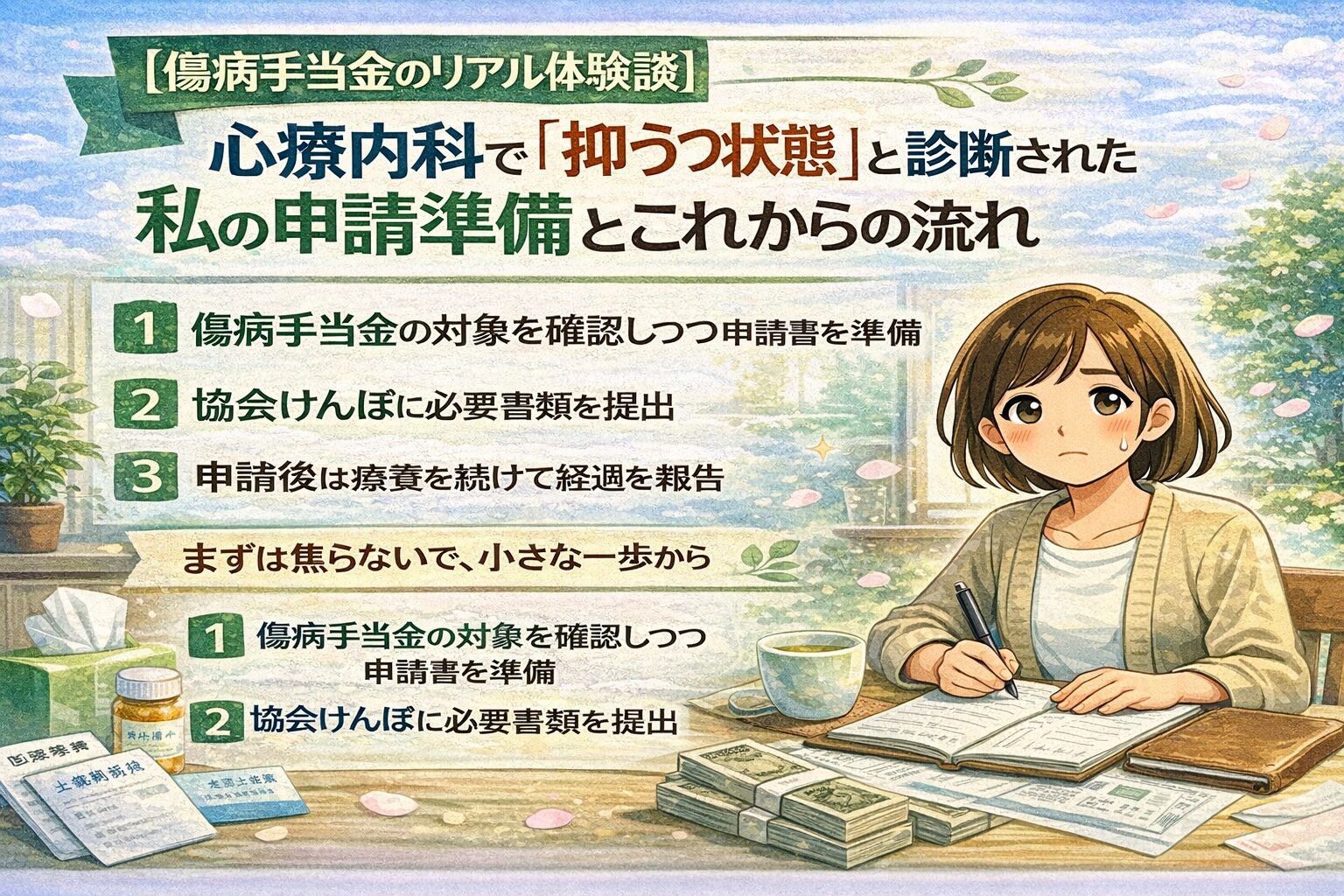第2話|【退職を控えた看護師のリアル】キャパオーバーから退職までに行った手続きと心の整理
キャパオーバーで心療内科を受診し、「抑うつ状態」と診断されてから、約1か月半。
いま私は、すべての手続きを終え、10月31日の退職日を静かに待っているところです。
この記事では、退職までに実際に行った手続きや、進めながら感じたことをまとめました。
これから退職を迎える方の、少しでも参考になればうれしいです🌿
診断書の提出と休養のスタート
9月中旬、心療内科で「抑うつ状態」と診断され、まずは1ヶ月の自宅療養が必要と言われました。
その日のうちに、診断書を職場へ速達で郵送しました。
簡単な手紙に感謝の気持ちを添えて送りました。
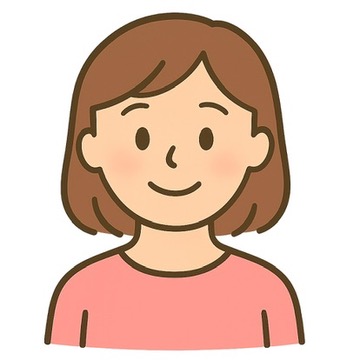
📄 私が診断書を送るときに添えた一文:
「主治医の勧めにより、しばらくの間自宅療養をさせていただくことになりました。
診断書を同封いたしますので、ご確認のほどよろしくお願いいたします。」
休養中は、職場からの連絡にも丁寧に対応しつつ、再診のたびに診断書を更新して郵送しました。
郵便局を出たとき、少し肩の力が抜けた気がしました。
診断書を送ったあと、主治医からはこんな言葉がありました。
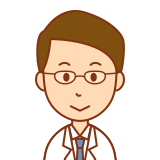
怖いと感じている職場へ、あなた自身が直接行くのはやめてください。
娘さんに電話してもらい、今後の対応は娘さんが行う意思を伝えてもらいましょう。
娘さんを“防波堤”にしてください。病状が悪化するのは避けたいですからね。
その言葉に、涙が出ました。
“自分を守るために距離を取っていいんだ”と、ようやく心から納得できた瞬間でした。
そしてその日から、少しずつ「怖い職場よりも、自分の回復を優先する」ことを意識するようになりました。
退職届の提出と気持ちの整理
1か月の療養を経て、「このままでは戻るのは難しい」と実感。
主治医とも相談のうえ、10月31日付で退職する決意を固めました。
退職届は便箋に自筆で記入し、白い封筒に入れて簡易書留で郵送しました。
便箋に文字を綴りながら、いろんな思いがこみ上げました。
お世話になった方々への感謝、申し訳なさ、そして少しの安堵。
書き終えたとき、「ここまでよく頑張ったな」と自分に言ってあげたくなりました。
退職後の健康保険と年金の切り替え準備
退職後は健康保険と年金の切り替えが必要になります。
私は退職日以降、国民健康保険と国民年金へ切り替える予定で、市役所での手続き準備を済ませました。
健康保険証の返却は、退職日前に郵送する予定です。
退職後の保険には次の3つの選択肢があります👇
- 任意継続被保険者として継続(最長2年)
- 家族の扶養に入る
- 国民健康保険に加入する
私の場合は一人暮らしなので、国保加入を選びました。
窓口での手続きは退職日の翌日から14日以内が目安とのことです。
傷病手当金の申請と提出準備
休養中は給与が止まるため、傷病手当金を申請することにしました。
主治医の記入欄・本人記入欄・事業主記入欄の3部構成で、退職前に職場へ依頼を済ませています。
今は、11月に協会けんぽへ提出できるように準備を整えているところです。
この手当金があるだけで、経済的にも心にも少し余裕が生まれました。
退職後も支給要件を満たしていれば継続できるため、忘れずに手続きを進めておきたいところです。
📚 あわせて読みたい
有給休暇の整理と引継ぎ
私は40日ほど有給が残っていましたが、療養を優先して消化しました。
引継ぎは、体調の良い日に少しずつメモをまとめ、信頼できる同僚に託しました。
「ありがとう」と伝えられたことが、心の救いになっています。
退職後に受け取る書類のチェック
退職後に届く書類も確認済みです。届いたら内容を必ず確認し、保管するようにしています。
- ✔ 離職票(失業給付申請用)
- ✔ 源泉徴収票(年末調整・確定申告用)
- ✔ 健康保険資格喪失証明書(国保・扶養手続き用)
まとめ|退職を待つこの時間を、少しでも穏やかに
いまは、すべての手続きを終えて退職日を待つのみ。
焦りも不安もありますが、どこか静かな気持ちで過ごしています。
ここまで来られたのは、主治医や同僚、そして支えてくれた人たちのおかげ。
そして何より、「自分を守る」という選択をした自分自身を、少し誇らしく感じています。
これからのことは、退職後の心と体の回復を見ながら、ゆっくり考えていこうと思います🍀
※ 本記事は筆者の実体験をもとにしています。制度内容は時期や地域により異なる場合があります。
詳細は所属先や各自治体・保険者にご確認ください。