職場に必ずいる“サボる人”|理不尽でも諦めるしかないのか?
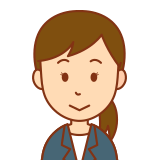
「どうして私ばかり仕事が増えるんだろう?」
「上司の前では働くフリをするのに、普段は全然動かない人がいる…」
どの職場にも“サボる人”はいます。私の職場も例外ではなく、働く人・サボる人はほぼ固定。真面目な人ほど仕事量が増えて疲弊し、サボる人は平気な顔で上司の前だけ取り繕う――理不尽さや虚しさを感じます。
💡この記事でわかること
- なぜ職場からサボる人が消えないのか(行動・心理の視点)
- 「期待」と人間関係がサボりに与える影響
- 理不尽と付き合いながら自分を守る働き方
働きアリの法則に見る“サボる人”の存在
生物学の示す「働きアリの法則」では、集団の中でよく働く2割・普通6割・ほとんど働かない2割
に分かれやすいとされます。この分布は人間の職場にもよく当てはまると感じます。
📊 アルアルな実感と調査の傾向
- 「頻繁にサボる」約2割+「たまにサボる」約4割=6割が何らかのサボり経験
- 「全くサボらない」人は約2割弱
つまり“働かない人がゼロ”の職場はほぼ存在しません。
これは「特定の誰かが悪い」以前に、集団には一定割合で生じる現象だと受け止める視点も大切です。
サボりと人間関係に共通する「期待」の役割
サボり行動と人間関係の悪化には、共通して 期待 が絡みます。
- 役割期待に応える=信頼が積み上がる
- 期待を下回る=不満・失望
- サボる人は周囲の期待値が低いので、たまに働くと驚かれるが安定した信頼は得にくい
- 人間関係では期待のすり合わせ不足が摩擦やストレスに直結

【職場の現実】期待を言語化・共有しないまま「察して」を続けるとズレが大きくなりやすい。
小さなズレの積み重ねは、職場全体の空気の悪化につながります。
「怠け」だけじゃない:サボる人が生まれる心理的背景
✅ 背景にある主な要因
- モチベーション低下(やりがい・評価が感じられない)
- 人間関係の悪化(摩擦・孤立・ハラスメント)
- 過度なストレスや心身不調(長時間労働・家庭/経済問題)
- 待遇への不満(「頑張っても報われない」感)
- サボりの習慣化(抜け出しにくい)
- 適性のミスマッチ・会社への不信感
多くは「性格の問題」より 環境×心理の結果。個人責めだけでは解決が進みにくい領域です。
サボる人の実態:現場で見える“動き方の差”
私の職場でも、サボる人と働く人の差は日常の小さな場面に表れます。
たとえば透析室では、技士が各ベッドのタイマー音に対応するとき、以前に文句を言った看護師を呼ぶのは避け、近くにいる別の看護師を選んで声をかけます。
つまり、サボる人は「タイマーをセットするだけでその場を離れてしまう」。
一方で、働く人は自分の受け持ち患者の近くを離れず、責任を持って対応する。
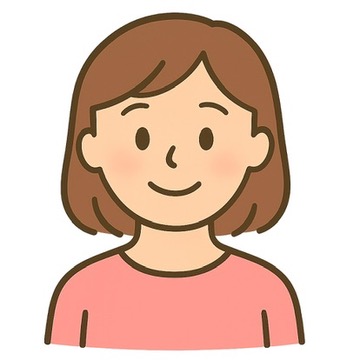
こうした場面を繰り返し見ると、働く人の負担がますます増え、サボる人はさらに“呼ばれにくい存在”になっていく――そんな悪循環が生まれます。
理不尽に飲まれないための「戦略的サボり」
発想を変えて、サボり=悪ではなく エネルギー配分の戦略 として取り入れる。
🛠 実践ミニガイド
- ムダ削減:目的の曖昧な会議や報告を圧縮する提案
- 小休憩ルーティン:60分に10分休むことで集中を回復
- 重要タスク集中:“今日の勝ち筋”を朝イチで3つに絞る
- 境界線を引く:巻き取るべきでない作業は丁寧に断る
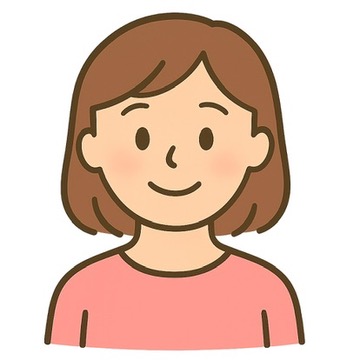
【働き方のヒント】サボる人にイライラし続けるより、自分の可処分エネルギーを守るほうが生産性もメンタルも安定します。
※ 可処分エネルギー=自分が自由に使える体力や気力
結論:諦めること=投げ出すことではない
悲しいけれど、どの職場にもサボる人はいます。完全にゼロにするのは現実的ではない。
だから私は「諦める」を選びました。

【私の答え】「不満が消えるわけではない。
それでも、自分に恥ずかしくない働き方を守る。
ときに冷めた目で見られても、胸を張れる選択を続ける。」
読んでくださったあなたの職場にも、きっと“サボる人”はいるはず。
そんなとき、あなたはどう受け止めますか?


